 大津百艘船の構想 大津百艘船の構想
信長のあと琵琶湖の水運に目を向けたのが秀吉であった。天正14年、15年ごろ(1586-1587)当時、坂本にあった城を大津に移し、従来の坂本城主・浅野長吉を初代大津城主とした。秀吉が天正11年(1583)に着工した大阪城は、翌年には大方の工事を終え、同城に住んでみて始めて政治、経済の中心が京都から大阪に移りつつあり、琵琶湖の水運を利用して運ばれる物資も京都へではなく、大阪を目指していることに気付いた。
このため従来の湖辺から山中越(坂本から山中町を経て京都へ至る道)で京都へ向かう坂本港に代え、大阪に通じる逢坂越から伏見街道に入る大津港が便利だと気付き、とにかく近江の拠点城を坂本から大津に移した。しかし当時の大津は、堅田や坂本ほど栄えておらず船も少なく、浅野長吉にとっては、いかにして琵琶湖の諸浦から大津に船を集めるかが、最大の課題であった。
|
 百艘船募集の定(さだめ)書 百艘船募集の定(さだめ)書
浅野長吉は、天正15年2月16日付け(1587)で大津居住の船持ちに加え坂本、堅田、木浜(このはま、守山市)など諸浦から百艘の船を集めるため、五カ条から成る定書(さだめがき)を立てた。
第一条 大津から出る荷物、旅人を他浦からの入船に乗らせることを禁じた。
第ニ条 たとえ大津の船であっても、浅野長吉の下で「役義」(公務)を努めない船、すなわち大津百艘船以外の船は、やはり大津からの荷物、旅人の積み出しを禁じた。
第三条 大津百艘船が、他浦で公事(くじ)船(公用船)として使用されることを禁じた。
第四条 長吉の下で、公事船として使役される場合の荷物の積み降ろしを船頭だけでやってはならないことを定めた。
第五条 浅野家の家中でも勝手に大津百艘船を使用することを禁じた。
 第四条の公事船の荷物の扱いに関する規定を除いては、いずれも大津百艘船の特権を保護するもので、大津百艘船が頭初から権力の厚い保護を受けていたことが判る。 第四条の公事船の荷物の扱いに関する規定を除いては、いずれも大津百艘船の特権を保護するもので、大津百艘船が頭初から権力の厚い保護を受けていたことが判る。
大津百艘船はこののち、天正17年2月15日(1584)には増田長盛から、同19年5月9日(1591)新光直頼から、文禄4年9月11日(1595)には京極高次など歴代の大津城主から同文の制札を受けている。また関が原の戦の翌年・慶長6年7月2日(1601)には、徳川家康時代最初の大津代官・大久保長安より同文の制札を受けており、秀吉の治世下、獲得した百艘船の特権が徳川の世まで引き継がれていった。
|
|
 船奉行と艫(とも)折回船 船奉行と艫(とも)折回船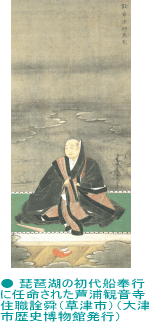
秀吉の湖上支配は、当初から何の障害もなく、着実に進展していったわけではない。大津と堅田をめぐる湖上特権の調整などは秀吉が最も苦慮した課題であった。
例えば天正11年(1583)12月12日付の堅田に出した浅野長吉の定書によれば、堅田の船は、どの浦へも回船できることになっていた。これに対し、同じ浅野長吉が天正15年2月16日付で大津宛に出した定書には、その第一条に大津からの荷物、旅人の運送には、他浦の船を使用することを禁じている。この二つの定書が矛盾していることは明らかで、両浦の特権の調整、融和が当面の緊急課題となってきた。秀吉は、この解決策としてニつの方法を用いた。
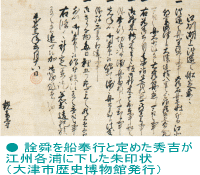 その一 船奉行の設置と任命 その一 船奉行の設置と任命
秀吉時代の琵琶湖全浦の船数は約ニ千艘。これらの船は、秀吉の下で芦浦観音寺住職詮舜(草津市)が統轄していた。同寺は戦国時代当初から湖南の渡湖地点・支那浦(草津市)を抑え、この地方に勢力を張っていた。秀吉は、天正19年(1591)この観音寺詮舜を正式に琵琶湖の船奉行に任命「江船諸浦」に朱印状をだした。
その二 とも折回船
とも折とは、船積みのため二艘の船が同時に着津したときには、先にとも(船の後部)を浜に着けた方から船積みを行わなければならないという船積みの順番に関する規定のことである。ところが琵琶湖のとも折回船はさらに複雑な内容を持っていた。というのは秀吉は、このとも折を駆使出来る浦を大津、堅田、八幡(近江八幡市)の三浦に限った。八幡がこの特権を保持したのは、秀吉のおいの秀次が天正13年(1585)より八幡山城主となっていたからだが、それはともかく、この新しい湖上水運の秩序を創立し、その頂点に堅田、大津を並存させることによって両浦のそれまでの特権を巧みに調整、融合させることにあった。
|
 江戸幕府と湖上水運 江戸幕府と湖上水運
慶長3年(1598)秀吉が逝き、家康が征夷大将軍に任命されると天下人としての活動を始め、琵琶湖水運に関する政策にも着手した。慶長6年(1601)5月、家康は徳川家の要人・大久保長安らを通じて観音寺に対し、これまで通り船奉行を務めることと、諸浦の船の調査を命じる一方、秀吉の代につくらせた琵琶湖の制度をそのまま継ぐことを認めさせるとともに、諸浦の「庄屋、船方」に改めて観音寺朝賢への船奉行任命を布告した。また翌7年(1602)には、百艘船の特権にも許可を与え、大久保長安名で改めて制札を与えた。
また最後まで残っていた堅田の水運に関する特権についても元和3年6月(1617)大津代官小野宗左衛門貞則が下した五ケ条の定書に、堅田の船はたとえ入船であっても大津から旅人、荷物を積み込む権利を認め、大津と並び堅田は幕府のもとで琵琶湖の盟主として認められた。
|
 西回り海運の整備と大津港 西回り海運の整備と大津港
近世前期、琵琶湖水運は、京都・大阪・東日本を結ぶ重要な幹線ルートとしての役割りをになっていたが、敦賀や小浜で陸揚げされた荷物が、人や馬の背で峠を越え、琵琶湖岸の港から湖上を大津へ運び、ここで再び陸揚げして京都や大阪へ陸送する。ところがこのコースには①峠越えの道で、一度に大量の荷物が運べない②積み替えのたびに問屋への口銭(手数料)がかかるなどの問題点があった。
こうした中で、大量の米を一度に運ぶために開発されたのが「西回海運」である。今まで敦賀や小浜で陸揚げしていた荷物をそのまま西へ運び、関門海峡から瀬戸内海に入って大阪まで直送、さらに紀伊半島を回って江戸に至るというもの。大阪までの航路は、寛永15年(1638)金沢藩が米百石を運んだのが最初。その後、江戸幕府の命を受けた河村瑞賢は、寛文12年(1672)出羽国・酒田(山形県)からの幕府年貢輸送に成功、西回航路がオープンした。
この航路の整備は、琵琶湖水運に大きな打撃を与えた。敦賀への米と大豆の入津量は、寛文年間(1661-1673)の年平均五56万俵をピークに、元禄年間(1688-1704)には半減し、享保年間(1716-1736)には5分の1と激減した。敦賀への入津量の減少は、そのまま湖上輸送の減少を意味した。
対策として琵琶湖北岸の塩津(西浅井郡)と敦賀の間に運河を開削し、船を通わせる計画が何度か試みられたがいずれも失敗に終わった。
この結果、寛文5年(1665)には102艘、元禄6年(1693)には107艘を数えた大津百艘船の数は、享保10年(1725)には47艘、明和3年(1766)には39艘と減少の一途をたどっていった。しかし琵琶湖周辺の地域や丹後(京都府)若狭(福井県)などからの米は引き続き湖上交通を利用して大津に集められ、琵琶湖を中心に周辺地域を結ぶ航路としての役割を果たしていた。
|
|
|
|
参考図書
大津市史、大津市教委発行 大津の歴史、大津市歴史博物館発行「琵琶湖の船」
|
| (曽我一夫記) |
|
|
|
|
|
|