 多羅尾地区のはじまり 多羅尾地区のはじまり
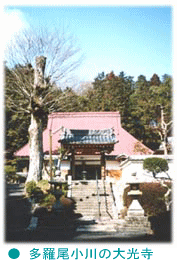
白鳳から奈良時代にかけては、近江大津宮の造営、遷都やその後の壬申の乱、聖武天皇時代には山背恭仁(くに)京への遷都と、信楽宮の造営など大和と山城を結ぶ朝廷の用件は多かったと思われる。
その都度、近江から大和国へは、草津や瀬田から信楽に入り、多羅尾から島ヶ原峠を越え、月ヶ瀬、柳生を通り、春日山を越えて大和に入るか、笠置に出て、そこから木津川を舟で下り、
奈良坂越えで大和国に入る「御幸道」(当時の名前)を使っていた。
また京都方面から伊賀、伊勢へ行くには、大津から瀬田に出て、田上不動越えで多羅尾に来るか、または瀬田、大石に出て富川、朝宮を経て多羅尾に入り、
ここから御斎(とぎ)峠を越えて伊賀上野へ出た。
この道は古くから「京街道」といわれる官道(今の国道)だった。このように多羅尾は、山の中の寒村だったが、
大和朝廷が近畿地方を治めるようになってから主要道路として多くの旅人に知られ、道中の“憩いの場”ともなっていた。
|
 多羅尾氏の誕生 多羅尾氏の誕生
 正應4年(1291)当時、信楽は藤原氏の一族・近衛氏の荘園だった。
関白となり、京都で政治をみていた近衛家基は、信楽荘を休息の場としていた。職を辞してからは信楽荘小川の館に隠居、永仁4年(1296)この地で亡くなった。
家基の子・経平も京都の朝廷で、左大臣の要職についていたが、身体が弱いため役を辞して信楽荘に帰っていた。
その時、経平と多羅尾の地侍の娘との間に男の子が生まれ、初め高山太郎と名乗っていたが、嘉元元年(1303)母の里・多羅尾の地名を姓として、名を師俊(もろとし)と改め、
武士となった。この師俊が現代まで27代続く多羅尾家の先祖。経平は文保2年(1318)師俊も正慶2年(1333)に亡くなり、祖父・家基、父・経平、師俊をはじめ多羅尾代々の墓は、
今も小川の大光寺に残っている。 正應4年(1291)当時、信楽は藤原氏の一族・近衛氏の荘園だった。
関白となり、京都で政治をみていた近衛家基は、信楽荘を休息の場としていた。職を辞してからは信楽荘小川の館に隠居、永仁4年(1296)この地で亡くなった。
家基の子・経平も京都の朝廷で、左大臣の要職についていたが、身体が弱いため役を辞して信楽荘に帰っていた。
その時、経平と多羅尾の地侍の娘との間に男の子が生まれ、初め高山太郎と名乗っていたが、嘉元元年(1303)母の里・多羅尾の地名を姓として、名を師俊(もろとし)と改め、
武士となった。この師俊が現代まで27代続く多羅尾家の先祖。経平は文保2年(1318)師俊も正慶2年(1333)に亡くなり、祖父・家基、父・経平、師俊をはじめ多羅尾代々の墓は、
今も小川の大光寺に残っている。
|
 戦国の武将・多羅尾光俊 戦国の武将・多羅尾光俊
戦国時代から安土、桃山時代にかけて信楽で、歴史上名を現したのは多羅尾14代目の光俊。
永正11年(1514)多羅尾に生まれ、成人して父・光吉より信楽の領地七千石を受け継ぎ、甲賀武士五十三家の一家として佐々木六角高頼の信楽代表となったが、
高頼が死んでからは織田信長に仕えた。
信長が安土に城を築き、全国統一の計画をたて始めた頃、伊賀国の豪族らが信長の命令に従わないばかりか、上野の平楽寺に集まって、
信長に抵抗する企てをたてていることが判った。信長は天正9年(1581)大軍を率いて伊勢、大和、近江三国から伊賀国を攻め、町や村を焼き払った。
この戦いに光俊は信長に味方して手柄をたてた。
|
 徳川家康・伊賀越えの難 徳川家康・伊賀越えの難
天正10年5月(1582)徳川家康は、織田信長から駿河国を配領したお礼に安土城を訪れた。
酒宴の席で信長は「和泉国(大阪府)の堺港は、各国の船が出入りして交易が盛んに行われている。
良い鉄砲や珍しい外国の品々があるので是非見て帰るように」とすすめた。
家康は、おもだった家来だけを連れて堺の町々を歩き、外国貿易の様子や店頭に並ぶ品々を見た上で、もう一度京都へ上り、信長に再会して帰ろうと、枚方まで来たところ、
京都から連絡が入り、今朝早く信長が本能寺(京都)で明智光秀の奇襲を受け、あえない最後を遂げたことが判った。
驚き悲しんだ家康は、少人数ではどうにもならず、その上、自分が光秀に狙われる危険性もあると考え、このまま間道づたいに三河に帰ることにした。
河内の山を越え、大和から山城国に出て、木津川を渡り、やっとのことで宇治田原(現在の京都府綴喜郡)に着いたが、この間、何度も山賊や野武士に襲われた。
|
 22年前の縁が命の恩人 22年前の縁が命の恩人
宇治田原城主・山田甚助の養子・藤左衛門父子は、家康一行を厚くもてなし、藤左衛門は早速、実家の父・多羅尾城主の光秀に早馬を出して連絡、
驚いた光俊は二男の光太、三男・光定を迎えに出し、藤左衛門とともに多羅尾城に出迎えた。家康がなぜ藤左衛門の言葉を信じて多羅尾に向かったのか。
それは22年前の永禄3年(1560)織田信長と今川義元の桶狭(おけはざま)の戦いの折、当時今川方に味方していた徳川元康(後の家康)の誘いを受け、
光俊が甲賀武士団を引き連れて元康の陣営にはせ参じ、刈屋城を焼き打ちして戦功をたて、元康から多くの賞金をもらった。
戦国時代、各大名は戦の時、地方の武士を戦闘員として募集。地方の豪族も武力を鍛え、軍資金を蓄えるために出稼ぎをしていたようだ。
家康は、遠い昔の縁を思い浮かべたのだろう。だが用心深い家康はすぐには城に入ろうとはせず、城の向かいの小高い茶山に腰をおろして城の中の様子を見守っていた。
光俊父子は、多羅尾の名物・干柿(ころ柿)や新茶を出してねぎらい、ようやく安心して城に入った。
住民総出で赤飯を炊いてもてなし、光俊は家来に命じて各峠を固めさせ、怪しい者は一人も多羅尾の中には入れないようにした。
家康一行は、堺を立って初めて一晩ぐっすり休むことが出来たという。
翌朝、光太、光定、藤左衛門とその家来に守られて御斎峠に出、そこから柘植(つげ)に向かい、加太(かぶと)峠を越えて、関から伊勢白子浜に無事到着した。
家康は、多羅尾兄弟にそれぞれ太刀を贈り、是非三河に来るよう伝え、船で三河国へ帰っていった。
この伊賀越えの難は、家康の一生にとって一番危険な事件といわれるだけに、家康と多羅尾家の関係は一層深いものとなった。
|
 天下取りは秀吉に傾く 天下取りは秀吉に傾く
信長が亡くなり、秀吉が信長の仇討ちをして勢力を伸ばしてくると、信長の遺族や家臣の中には、心よく思わないものが出てきた。
中でも北陸の柴田勝家や信長の三男・信孝と滝川一益などは、心の中で秀吉を何とかしようと密談を交わしていた。
この情報を耳にした秀吉は、天正11年(1583)正月、雪解けまでに伊勢の一益と岐阜の信孝をたたいておこうと、大軍を近江国・草津に集めた。
一方、浅野長政に山城国から信楽、伊賀に出て、柘植から加太越えに一益の亀山城を攻めるよう命じた。
その手始めに長政は、多羅尾光俊の四男・光量(みつかず)のいる和束の別所城を攻め、信楽に押し入ろうとしたが、逆に夜討ちにあって、退却させられた。

長政は、このあと光俊と戦うよりは和睦して話し合いで通してもらおうと、自分の一人娘を光俊の三男・光定の嫁にもらってもらえないかと光俊に持ちかけた。
光俊も秀吉と戦っては損だと思っていたからすぐにまとまり、長政は戦わずして亀山城を攻め落とすことが出来た。また光俊も浅野氏と縁を結んで一歩秀吉に近づくことになった。
こうして光俊は天正14年頃(1586)には、八万千石の大豪族となり、光俊は小川に本城を、多羅尾城には後継ぎの光太を、田上の里城には三男・光定を置き、
和束の別所城には四男・光量を配して不敗の体制を整えたのだが…。(上終わり)
|
参考図書
・多羅尾の歴史物語 多羅尾郷土史研究会偏発行 杉原 信一著
・甲賀史 上、中、下
・家康と伊賀越えの危難 川崎記孝著 日本図書刊行会発行
|
| (曽我一夫記) |
|
|
|
|