幨恀丗揤堜愳偲側偭偰偄傞憪捗愳丂
偙偺恀壓偑僩儞僱儖偱椃恖偨偪偼偙偙偐傜搆曕偱搉偭偨丅
偙偺恀壓偑僩儞僱儖偱椃恖偨偪偼偙偙偐傜搆曕偱搉偭偨丅
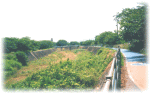
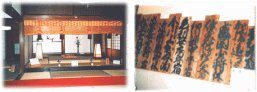 |
幨恀嵍丗杮恮撪墱偺崅嵗丄揤峜偺偍攽傝強 幨恀塃丗杮恮偵媥攽偟偨彅戝柤偺昞嶥 |

| 乽塃搶奀摴偄偣傒偪乿乽嵍拞嶳摴旤偺偫乿屆晽側壩戃偺偮偄偨摴昗(崅偝4.45嘼)偑憪捗巗戝楬(偍偍偠)堦挌栚偺憪捗愳僩儞僱儖偺掔杊榚偵寶偭偰偄傞丅偙偺愳偼揤堜愳偱掔杊偺崅偝偑栺8嘼傕偁傝丄柧帯19擭乮1886乯偙偺僩儞僱儖偑弌棃傞傑偱偼丄拞嶳摴傪捠傞椃恖偼丄掔杊偺忋傑偱搊傝丄偦偙偐傜搆曕偱愳傪搉偭偰庣嶳亅敧敠亅娭儢尨傪宱偰峕屗偵岦偐偭偨丅 丂塃懁偺憪捗愳掔杊増偄偺搶奀摴傪恑傓偲愇晹亅搚嶳亅娭傪墇偊偰峕屗傊丅嫗搒傊偼拞嶳摴偲偼斀懳偺奨摴嬝傪捠偭偰戝捗傪宱偰嫗搒傊丅傑偨偺傫傃傝嫗搒傊偺椃傪妝偟傒偨偄偲偄偆椃恖偼丄奨摴嬝偺栴憅偐傜栴嫶奨摴偵擖傝丄栴嫶峘偐傜戝娵巕慏乮昐愇廙乯偵忔傝崬傒丄栺2帪娫偐偗偰戝捗偺愇応傑偱偺廙椃傪枮媔丄偙偙偐傜埀嶁偺娭亅嶳壢亅搶嶳傪宱偰廔拝晉偺嫗搒丒嶰忦偵拝偄偨丅 |
|
| 幨恀忋丗丂憪捗廻偺奨摴嬝偵偨偩堦尙巆傞栘壆杮恮丅丂撍偒摉偨傝偑憪捗愳僩儞僱儖丅丂杮恮偐傜栺1.3噏偑廻応偺奨摴嬝丂丂 乮憪捗愳傛傝斀懳曽岦乯丂 幨恀塃丗 憪捗愳僩儞僱儖塃懁偵偁傞丂丂 乽嵍丗拞嶳摴旤偺偫乿丂乽塃丗搶奀摴偄偣傒偪乿偺摴昗丂 |
|
嫗搒偼峕屗偐傜悢偊偰53師栚偺廻応偩偐傜憪捗偼52師栚丅拞嶳摴偱偼栘慮楬68師栚偺廻応偩偭偨丅偄偢傟偵偟偰傕憪捗偲嫗搒偼栚偲旲偺嫍棧丄墹忛偵嬤偔拞嶳摴偲搶奀摴偺暘婒揰丄偦傟偵埳惃摴傊偺嬋偑傝妏偲偄偆梫徴偩偗偵憪捗廻傪棙梡偡傞椃恖偼揤峜丄戝柤丄暥恖丄杗媞側偳怓乆側恖偑懡偐偭偨丅 |
|
憪捗偺抧柤丂丂 丂姍憅枛婜(1275)帪廆(偠偟傘偆)偺奐慶丒堦曊偺嫵壔曊楌傪昤偄偨乽堦曊忋恖奊揱乿偺姫幍偵乽堦曊偑搶崙弰楌偺偺偪旜挘丄旤擹傪宱偰嫗搒偵岦偐偆搑拞丄憪捗偵偍偄偰栭拞丄偵傢偐偵棆偵偁偄丄堦曊偺柌偺拞偵埳惃戝恄媨傗嶳墹偺恄偑偁傜傢傟丄晄怣怱偺傕偺偳傕偵懳偟丄嶳恄偨偪偑偙傟傪敱偟偨偨傔丄昦婥偵側偭偨傕偺偑懡偔偁傞偙偲傪崘偘偨丅偼偨偟偰梻挬丄堦曊偵廬偆帪廆偺搆偺拞偱13恖傕偺昦恖偑偄偨偙偲傪婰偟偰偄傞乿偙傟偑憪捗偺抧柤偑暥專忋偱堦斣憗偔弌尰偟偨偲偄傢傟偰偄傞丅 |
|
壠峃偑嬤悽廻墂惂搙傪婲摦丂丂 丂峕屗帪戙傛傝慜偺憪捗晅嬤偑偳偺傛偆偱偁偭偨偐偼敾傜側偄偑丄憪捗巗忛偼丄屆戙偺嬤峕嫗偁傞偄偼暯埨嫗偺崰偐傜搶奀摴偲搶嶳摴(屻偺拞嶳摴)偺暘婒揰偲偄偆埵抲偵偁偭偨丅愴崙帪戙偵擖偭偰怐揷怣挿丄朙恇廏媑丄摽愳壠峃偲丄帪戙偛偲偵廻応揑婡擻傪崅傔偰峴偒丄宑挿屲擭(1600)娭儢尨偺崌愴偱彑棙傪廂傔丄惌尃傪庤拞偵偟偨摽愳壠峃偼宑挿榋擭(1601)懕偄偰摨幍擭偵搶奀摴偲拞嶳摴傪惍旛丄姲塱12擭(1635乯嶲嬑岎戙偺巒傑偭偨擭偵丄揷拞嬨憼丄揷拞幍嵍塹栧偑杮恮怑傪攓柦丄峕屗帪戙傪捠偠偰偙偺擇杮恮偑憪捗廻偺拞妀偲側偭偨丅 丂偙偆偟偰憪捗廻偼丄廻傪峔惉偡傞奨摴丄杮恮丄榚杮恮丄椃饽壆丄栤壆応丄摴昗丄崅嶥応側偳偐傜惉傝丄尦榎14擭(1701)偺乽憪捗挰柧嵶挔乿偵傛傟偽丄壠悢294尙丄恖岺2048恖丅暥壔14擭(1817)偱偼壠悢432尙丄恖岥2648恖傪悢偊丄揤曐14擭(1843)偺乽搶奀摴廻懞戝奣挔乿偵傛傞偲11挰53娫敿(栺1.3嘸)偺墲娨傪偼偝傫偱杮恮2尙丄榚杮恮2尙傪偼偠傔戝彫72尙偺椃饽壆偑尙傪楢偹偰偄偨丅峕屗傑偱偺嫍棧偼搶奀摴偱115棦梋傝(449.6嘸)椬傝偺愇晹廻傑偱2棦敿17挰54娫(栺11.9嘸)戝捗廻傑偱3棦敿6挰(栺14.3嘸)拞嶳摴庣嶳廻傑偱偼1棦敿(栺5.8嘸)栴嫶傑偱1棦8挰(栺4.5嘸)偱偁偭偨丅 栴嫶偼搶奀摴偺廻応偱偼側偔丄憪捗廻偵曪妵偝傟傞戝捗丒愇応傊偺搉偟応偲偟偰埵抲偯偗傜傟丄宲棫偺婡擻傪桳偟偰偄偨丅 |
|
廻応偺婡擻丂丂丂 丂廻応偼嶳摴丄奀摴傪栤傢偢丄岎捠偺梫徴偵惗傑傟傞偲偄傢傟傞偑憪捗偼傑偝偵偦偺捠傝丅偦偺婡擻偼丄孯帠揑側惇椃偐傜堦斒揑側摴拞偵帄傞傑偱丄懡彮偵偐偐傢傜偢廻攽偲摨帪偵壿暔偺塣憲偑晄壜寚偺忦審偱偁傝丄帪偵偼娭強偺栶妱傕壽偣傜傟偰偄偨丅愴崙帪戙偺偁偲丄摽愳枊晎偺憂棫偱愴偼彮側偔側偭偨偑丄偦傟偱傕彨孯忋棇偺嫙曭偼峴孯偵戙傢傞傕偺偱丄姲塱11擭彨孯壠岝偺忋棇偺嫙曭偼憤惃30枩7愮恖梋偵媦傫偩丅偦偺揰椺擭偺嶲嬑岎戙側偳偼丄彨孯偵懳偡傞彅戝柤偺惤堄偺帵偟偳偙傠偱丄堦庬偺峴孯偱偁偭偨丅偦偺傛偆側娭學偐傜姲塱枛擭偵偼丄憪捗傪娷傓搶奀摴偺奺廻偵懳偟偰揱攏昐摢傪忢抲偝偣傞側偳廻墂惂搙傪姰慡側傕偺偵偟偰偄偭偨丅 丂 丂傑偨廻偱偼丄摴拞曭峴偲廻偺幚嵺偺娗棟偵摉偨傞慥強斔偺擇廳偺巟攝傪庴偗丄斔丄曭峴偺柤偵傛偭偰弌偝傟傞奺庬偺怗彂偼丄弴師廻憲傝偱夞憲偝傟廻栶恖偑彂偒幨偟偨丅傑偨昁梫偑偁傟偽奀摴丄嶳摴偺暘婒揰偲側偭偰偄傞捛暘尒晅(摴昗偺偁傞強)偵崅嶥応傪愝偗丄枅擔悢枃偺崅嶥偑宖偘傜傟丄偙偺崅嶥偺娗棟偼摿偵棷堄偟丄掔杊偺寛夡偺嫲傟偑偁傞偲偒偼丄栺1嘸棧傟偨棫栘恄幮傑偱塣傇偙偲偑媊柋偯偗傜傟傞側偳嵟戝偺拲堄偑暐傢傟偰偄偨丅 |
|
杮恮偺屭媞偲宱塩丂丂 丂杮恮偼丄廻応偵偍偗傞戙昞偩偗偵栧峔偊偱敀廎丄尯娭傪旛偊丄彂堾憿傝偱廻撪偱偼嵟傕執梕傪屩偭偰偄偨丅幒挰帪戙丄擇戙彨孯懌棙媊慒偑忋棇偺嵺丄椃廻偲偟偰巊偭偨偺偑巒傑傝偱丄姲塱婜(1624-44)偺嶲嬑岎戙偐傜杮恮偺媥攽偼岞壠丄捄巊丄堾巊丄栧愓丄戝柤側偳崅婱側恖偵尷傜傟丄杮恮偺壠奿偼廻撪偵偍偄偰偼崅偔丄摉庡偼懷搧傪嫋偝傟丄廻栶恖傗懞栶恖側偳偺梫怑傪寭偹丄廻応偺塣塩偵偐偐傢偭偰偄偨丅 丂杮恮偺宱塩柺傪傒傞偲丄杮恮偼椃饽壆偲堎側傝丄媥攽偺椏嬥偵掕傔偑側偔丄戝柤偨偪偺壓帓嬥偵傛偭偰宱塩偑惉傝棫偭偰偄偨丅偦偺偨傔戝柤偨偪傕斔嵿惌偑弫偄梋桾偑偁傞帪婜偵偼丄奺壠偺屩傝傗尒塰傕偁偭偰壓帓嬥偼斾妑揑偵朙晉偱偁偭偨偑丄枊枛婜偵側偭偰斔嵿惌偑嬯偟偔側傞偲壓帓嬥偑尭彮偡傞偙偲偵側偭偨丅偟偐偟杮恮偱偼椃饽壆偺傛偆偵堦斒偺椃恖傪媥攽偝偣傞偙偲偼嬛偠傜傟偰偄偨偨傔宱塩偼師戞偵嬯偟偔側偭偰偄偭偨丅偟偐偟幍嵍塹栧杮恮偼丄栘壆杮恮偲傕屇偽傟丄暃嬈偵嵽栘彜傪塩傫偱偄偨偺偱宱塩柺偱偼傑偩宐傑傟偰偄偨傛偆偩丅摿偵枊枛婜偺憶慠偲偟偨悽忣偵偁偭偰偼榓媨崀壟傗彨孯壠栁忋棇側偳偺戝婯柾捠峴偑偟偽偟偽峴傢傟傞偙偲偵傛偭偰廻偦偺傕偺傊偺晧扴偺憹戝偼傕偪傠傫杮恮傊偺塭嬁傕彮側偔側偐偭偨丅 |
|
媥攽偟偨恖払丂 丂嬨憼杮恮偺巎椏偑側偔丄尰懚偡傞栘壆杮恮偵巆傞尦榎婜偐傜柧帯婜偵帄傞180嶜偺乽戝暉挔乿偵傛傞偲丄悢懡偔偺恖乆偑媥攽偟偰偄傞丅峜彈榓媨丄彨孯壠帩傪偼偠傔丄愒曚帠審偱桳柤側戝愇撪憼彆傗媑椙忋栰夘丄愺栰撪彔摢丄僪僀僣恖堛巘僔乕儃儖僩丄枊枛偵妶桇偟偨怴愶慻偺搚曽嵨嶰側偳楌巎偺昞晳戜傊搊応偟偰偔傞恖乆丅傑偨奺斔戝柤偺嶲嬑岎戙傗棶媴巊愡丄挬慛恖巊愡偺峴楍丄偦偟偰彨孯傊偺專忋偺偨傔偺捒昳傗捒廱側偳偝傑偞傑側捠峴偑偁偭偨丅傑偨枅擭1寧偵偼擭摢巊偑峕屗偐傜嫗搒傊丄巐寧偵偼椺暭巊偑嫗搒偐傜擔岝搶徠媨傊丄5寧偵偼乽偍拑氣摴拞乿側偳偺掕椺屼梡捠峴偑擭娫丄10審傕偁偭偨丅偙偺傎偐暥恖丄杗媞偺媥攽傕懡偔丄椃饽壆偼椃恖偺憟扗愴傪墘偢傞偙偲偑偁傝憡屳偵怽偟崌傢偣丄潀彂傪嶌偭偰廻撪偺峧婭弆惓傪恾偭偰偄偨丅 |
|
戞13夞丂丂亅 搶奀摴憪捗廻 亅丂METRO No.139丂丂丂丂
